こんにちは、草食系高校教師です。
今日は「【中学校・高校】暗記型教育から思考型教育へ 〜知識編重型からの脱却〜」をお伝えします。
2020年、私たちは「答えのない時代」を生きています。
昨今では新型コロナウイルス、近い未来ではAI時代といった、数年前、いや数ヶ月前まで考えられなかったこと、つまり「未知なこと」や「予測不能なこと」が起きています、または起きようとしています。
これらの変化の速度は、人間の予想をはるかに越え、ますます加速しています。10年前に、1人1台スマートフォンを持っている時代を誰が想像できたでしょうか。また、5年前に生徒1人1台ダブレットを持ち、授業で使うことを誰が予測したでしょうか。
「答えのない時代」では「答えのない問題」を考える思考力が大切になってくるでしょう。教員に何ができるか。見ていきましょう。

思考型教育をきっかけに自分の意見を言える生徒が増えてくれれば嬉しいですね。
知識編重型からの脱却はできる?
2015年くらいから日本の教育において重要視されてきたテーマが、アクティブラーニングです。
「詰め込み教育」「一方通行」「講義形式」と揶揄されることの多い、昔ながらの知識偏重型の授業から脱し、体験学習や調査学習、ペアワーク、グループワークやディスカッションなどを通じて、生徒が「自ら能動的に学ぶ力」を身に付けられる教育へと変わっていこうという動きが盛んになりました。
実際、学校現場ではアクティブラーニングへ方向転換しようとする動きが多くありました。講師を呼んで校内研修を実施したり、他校の実践例を見学しに行ったりしました。しかし、どの先生も懸念されていたのが「受験対策ができているか」です。
もちろん「生徒が能動的に学ぶ力」を育てるための学習ですので、アクティブラーニングをすることによって自主的に学習することにつながるのかもしれませんが、やはり教員は心配になります。
結果がわかっている方法と結果がわからない方法を比べると前者を取りますよね?
それと同じで、結果が見えない分、この方法が適切なのかがわからなくなります。
アクティブラーニングが良い方法であることはわかっています。
しかし、受験システムが変わらなければいつまで経っても「知識偏重型」からの脱却は難しいのではないかと思います。
答えのない問題に取り組む
日本は、教科書や問題集を見てわかるように、正解を導き出す問題が多いです。
暗記していなければ解けない問題が多いため、授業がどうしても解答を導き出す内容に偏ってしまいがちです。
しかし、答えのない時代を生きるためには、暗記型教育よりも思考型教育が必要になるでしょう。以下のAとBの会話をご覧ください。
A

小野、2番のカッコに入るものは?

はい、海洋プラスチックゴミです。
B

小野、海洋プラスチックゴミってどうやったら減らせると思う?

はい、僕は1人1人の意識の問題だと思います。

その1人1人の意識はどうやって変えられる? 今、小野が「プラスチックゴミを減らして」と言われたらどんな行動を起こす?

これは世界の環境問題につながる。「1人1人の意識はどうやって変えられるか」と「変えてくださいと言われたらどんな行動を起こすか」を考えよう。
これまでは「A」の教育でしたが、これからは「B」の教育に移行する方が、冒頭で述べた「答えのない問題」を考える思考力につながるのではないでしょうか。。。
現在の日本は、暗記7割:思考3割と言われています。2020年度から大学入学共通テストに変わり、傾向も変わります。思考力を問う形式の問題はどのくらい出題されるのでしょうか。
教員はティーチャーではなくファシリテーターに
探求学習や答えのない問題に取り組むときは「ティーチャー=先生」ではなく「ファシリテーター=促進者」に徹することが大切だと思います。
生徒が考え続けられるように、励ましたり少しヒントを与えたりすることが教員の役目だと思います。教員の性でどうしても教えたくなってしまいますが、教えるのではなく質問を投げかけて、気づきを与えるのが今後の教員の形なのではないでしょうか。

あくまでも生徒が主役で、教員が引き立て役です。与えすぎず、与えなさすぎずと言ったところです!
オススメ書籍
最後に
今日は「【中学校・高校】暗記型教育から思考型教育へ 〜知識編重型からの脱却〜」をお伝えしました。
時代の変化とともに教育内容が変化してきましたが、求める生徒像も変化させていかなければいけないのかもしれませんね。
「未知なこと」や「予測不能なこと」が起きたときの問題解決方法を導き出すためにも思考力を鍛える必要がありますよね。
本日は以上です。ありがとうございました。







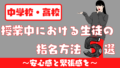
コメント