こんにちは、草食系高校教師です。
今日は「【中学校・高校】授業中の生徒の指名方法5選 〜授業に安心感と緊張感を〜」をお伝えします。
教育者である皆様は授業中の生徒の指名をどのように行なっていますでしょうか。または、どのような狙いで生徒を当てていますでしょうか。

今日は生徒を指名する理由と方法をお伝えしまっせー!
生徒を指名する理由
生徒を指名する理由は主に2つあると思います。それでは見ていきましょう。
緊張感を持たせるため
生徒を指名をすることで、教室内にある程度の緊張感を持たせます。その緊張感が生徒の集中力にブーストをかけてくれる一助になります。
そして、「指名されて答えられなかった」というのは人間心理からして、劣等感や恥ずかしさを少なからず感じると思います。
そのため「指名されたらしっかりと答えられるように話を聞こう、集中しよう」という思考回路になってくれればという願いが込められています。
生徒の理解度を確認
生徒を指名して、答えさせることによって生徒の理解度を知ることができます。
教員は生徒1人1人の実力をある程度把握していると思います。問題レベルと生徒レベルを見極めて、「この生徒がこの問題を間違えたからもうちょっと詳しく説明しよう」と別の角度からアプローチするサインにもなります。
生徒を指名する方法
自由指名
日本では王道の方法で、授業者が発問をして生徒が自由に挙手するタイプです。
生徒の自主性を重んじる方法だとは思いますが、問題点として、発言する生徒が偏ってしまうことです。積極的に人前で発言することを躊躇わずにできる生徒はいいですが、問題の答えをわかっていたとしても恥ずかしさや怖さのために発言できない生徒にとっては挙手しにくいでしょう。
実は学年が上がれば上がるほど、この「自由指名」は機能しなくなります。学校のレベルや雰囲気にもよりますが、高校3年生で「この問題わかる人?」と聞いても、まず手を上げる生徒はほとんどいないでしょう。
理由は、同調圧力でしょう。「出る杭は打たれる」のように、目立つ存在になると変な目で見られたり、いじめの対象にされたりするといったところです。
順番指名
座席の縦列や横列の生徒を順番に指名していくタイプです。該当の列の生徒は必ず答える順番が来るため、覚悟や準備ができます。
縦列や横列を決めるときに、ゲーム制を持たせるために1番前の列の生徒にジャンケンをさせることもあります。(少しリスクがあるので頻繁にはしません)
ランダム指名
ランダムに生徒を指名していくタイプです。これが1番緊張感を高められることができ、一気に教室の雰囲気が締まります。
私は、授業の雰囲気が悪い時や生徒が集中していないと感じたときにこの方法を使い、雰囲気を変えるようにしています。
生徒にとっては1番嫌な指名方法ですので、ゲーム性を持たせるために、iPad(タブレット)のストップウォッチ機能を使って、下二桁の数字の出席番号の生徒を指名していました。この方法なら当てられた生徒からも反感を買いません。
意図的指名
問題レベルに応じて意図的に指名するタイプです。
「この生徒がこの問題を間違えたらちょっと詳しく説明しよう」と教員が思う生徒の理解度と実際の生徒理解度の乖離を防ぐためです。
基本的に、授業学級の中の下〜中の中くらいの生徒向けに授業を行うのが一般的ですが、私は授業内の問題レベルを3段階に分けていたのでそれぞれの問題で該当する生徒に指名してました。
英語で指名
ランダム指名に近いですが、日本語で「♪どれにしようかな神様の言うとおり」とあると思います。それの英語バージョンだと思ってください。
私は英語科なので、これを頻繁に使いますが、言うたびに「何それ!教えて」と結構盛り上がります。
参考までに下に載せておきます。国や地域によって違うバージョンがありますので検索してみてください。英語科以外の先生がすると「すげえ」と言われるかもしれませんよ!笑
英語バージョン
Eenie, meenie, miney, moe,
Catch a tiger by the toe,
If he hollers let him go,
Eenie, meenie, miney, moe.
オススメ書籍
最後に
今日は「【中学校・高校】授業中の生徒の指名方法5選 〜授業に安心感と緊張感を〜」をお伝えしました。
意図や目的を持っての指名だと思いますが、ある程度の緊張感を持たせられるランダム指名が有効な手段だと思ってました。
本日は以上です。ありがとうございました。




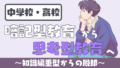

コメント