こんにちは、草食系高校教師です。
今日は「【中学校・高校】教員が知るべき机間巡視(机間指導)をする5つの理由 〜授業づくりのために〜」をお伝えします。
みなさん机間巡視はしているでしょうか。そして、何を意識しているでしょうか。
今日は私が考える机間巡視をする理由を5つご紹介します。

それでは見ていきましょう!
机間巡視とは
教員が授業中に児童・生徒の座席を巡回し、個別に学習状況のアドバイス・指導・観察をすることです。
生徒1人1人とコミュニケーションが取れる大切な時間になります。
机間巡視をする理由
私が机間巡視をするときに心掛けている5つのことをお伝えします。
①生徒の学習理解度の確認する
教員が授業で説明した内容や気づいてほしい授業の狙いを生徒がしっかりと理解しているかを確認します。
説明をした後に生徒が問題を解いたり、考えたりする時間を作ると思いますが、教員の説明が適切であったかを期間巡視で確認することができます。
私は授業担当するクラスで、学力が真ん中〜上位くらいである生徒を「ターゲット生徒」ととして、その生徒の理解が乏しければ、私の説明が不十分・不適切であったと感じています。
さらに、巡視をしてほとんどの生徒が間違っている問題がある場合は、ヒントを出したりその問題に時間をかけて行ったりしています。

生徒の理解度がよくわかりますね!
②アドバイスをする
悩んでいる生徒や少しヒントを与えたら答えられそうな生徒にはアドバイスをします。また、アドバイスを求めてくる生徒にも助言をします。
しかし、ヒントをあまり多く出さずに、気づきを与えるような声かけをするようにしています。どうしても生徒からアドバイスを求められると教員は得意げになってあれこれ伝えたくなりますが、生徒に考えさせるためにぐっと我慢しましょう。
また、自分で調べられることは生徒に調べさせた方が良いと思います。私は英語科ですので、「先生、この単語の意味教えてください」と聞かれますが、「文明機器(辞書)持ってるんだから自分で調べろよー」と受け流すようにしています。
「先生、教えてくれなかった」とややこしい生徒の場合は別ですよ!笑
③その後の授業計画を立てる
生徒の理解度によってその後の授業展開を変えています。
生徒の理解度が高ければ、その後の説明を短くしたり、次の活動を縮小したりしています。対照的に、生徒の理解度が低ければ、もっと詳しく説明をしたり、活動を増やしたりしています。
わかっているのに同じ活動をしても生産的ではありませんし、わからない状況で次から次へと授業を進んでいけば生徒の不満が溜まることでしょう。
臨機応変な対応です!
④生徒に緊張感を与える
クラス全体で説明や話をすると、聞いていない注意散漫な生徒が散見されます。しかし、机間巡視は「1人1人を見ている」感を出すことができるため、生徒に緊張感を与えることができます。
さらに、生徒は怒られないようにしようと課題に取り組もうとするため、教員は無言のプレッシャーを与えることができます。
⑤生徒を褒める
難しい問題ができた生徒や今までできない問題が解けるようになった生徒をとにかく褒めます。
生徒は褒められると嬉しくなり、もっと頑張ろうとする生徒が多いため、コミュニケーションの1つとしてとても大切だと思います。
オススメ書籍
最後に
今日は「【中学校・高校】教員が知るべき机間巡視(机間指導)をする5つの理由 〜授業づくりのために〜」をお伝えしました。
普段当たり前に行っている机間巡視ですが、文字化すると、改めてその行動の大切さがわかりました。ぜひ参考にしていただければと思います。
本日は以上です。ありがとうございました。




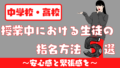

コメント