こんにちは、草食系高校教師です。
今日は「【中学校・高校】定期テスト(考査)の留意点と効率的な作り方」をお伝えします。
定期テスト(考査)は生徒の理解度を確認できたり、授業の反省をしたりできる教員として成長できる大きな機会です。
毎回作成している定期テストですが、今回は文字化して改めて定期試験について考えてみようと思います。

定期試験作成の注意点をお伝えしますよー!!
テスト作成時の留意点
私が実践している留意点を5つお伝えします。これまで3校の私立学校に勤めてきて、教えてもらったことと自ら考えて実践していることをお伝えします。
ぜひご覧ください。
①平均点を60点前後にする
平均点の基準が学校で決められています。
「平均点を◯◯点くらいにするように」と教務部から試験に関しての説明があると思います。
学校によって平均点は様々だと思いますが、基本は60点前後です。
②難易度を3段階に分ける
テスト作成時に、難易度を「A・B・C」の3段階に分けています。
点数配分や狙いをそれぞれ変えています。
A:基礎問題 50%
B:応用問題 30%
C:難易度の高い問題 20%
③テスト作成は2週間前〜1週間前
テスト作成は基本的に2週間前〜1週間前までの完成が望ましいです。
これは完全に学校によって様々ですが、「当日までに完成すれば良い」というゆるい学校もありますし、「1週間前までに教科主任に提出」と厳格なルールがある学校もあります。
同学年で2人以上の教科(科目)担当者がいる場合は、単元ごとに分けて作成するか、学期ごとに担当者を分けて作成をすることが多いでしょう。
作成後は担当者間で確認をします。
担当者によっては「ここ重点的に教えていないから別の問題に差し替えて欲しい」や「ここの問題難しすぎないですか」と訂正や提案がありますので、テスト当日までに確認作業を繰り返して、完成となります。
④試験時間の80%を生徒に使わせるようにする
テスト時間の80%を解答時間、残り20%を見直しの時間となるようにテストを作成するのが望ましいと言われています。50分の試験時間であれば、40分を解答時間、10分を見直しの時間となります。
私が初任の頃に勤めていた私立学校では「開始30分以内に終了するテストは作成者が悪い」との風潮があったため、上記の割合で作成するよう教わりました。
私は英語科ですので、時間配分はどうにでもなりますが、副教科の先生はとても苦労されていたのを覚えています。学校によってルールは違いますし、現在の勤務校は10分で終わったテストを作成しても何も言われません。
稀に、10分で終わるテストを作成する方がいますが、あれはだめです。
⑤テスト内容
テスト内容は「テスト範囲の内容」と言ってしまえば終わりですが、授業中に重点的に取り組んだ内容を出題するようにしています。
また、その学校の生徒が進学先に多い高校や大学をピックアップして傾向を似せた問題を出題するようにしています。
テスト作成にあたって
基本的にほとんどの先生がワードを使いテストを作成しています。
希にエクセルや一太郎派がいますが、問題作成はワードの方が扱いやすいと思っています。
テスト作成のフォーマットのルールが学校や教科や科目ごとにある場合があります。以下、これまでに勤めた学校のルールをお伝えします。
そして、私は以下のような表紙をつけていました。

テストの作成時間
私は1つのテスト作成(解答含)に平均3時間くらい費やしています。
もちろん、中1英語の試験作成は範囲が少ないため1時間で終了する場合もありますし、高3の難関大志望者対象授業の試験作成をする場合は5時間ほど費やすこともあります。

テストメーカーは使わないの?

基本的には使うけど、学校のレベルによっては使えない場合もあるね!
解答用紙と模範解答の作成
テスト作成は問題用紙作成・解答用紙作成・模範解答の3つを作成して終了となります。
私は上記のように問題作成をワード、解答用紙作成をエクセルで作成しています。解答用紙作成にエクセルを使っている理由は、模範解答作成しやすいためと解答率等を分析をするためです。
以下私がよく使っている解答用紙になります。

効率的なテストの作成方法
私が実際に行っているテストの作成方法をお伝えします。
まず大前提に、各教科書会社が提供しているテストメーカーを使います。各会社によって作成方法は異なりますが、教科書の試験範囲や単元を入力し、問題の種類を選択すれば基本的に作成することができます。
しかし、生徒のレベルによっては難しすぎる問題がありますし、授業者の狙いと違う場合がありますので半分以上は自作という先生もいるのではないでしょうか。
今日はその自作の部分の効率的な作成についてお伝えします。

テスト作成から早く解放されたいですよね!
①過年度の考査を見る
昨年度担当した教員に見せてもらうか過年度の考査が共有フォルダにあればそこをチェックしましょう!
進度はほとんど同じだと思うので、真似できるところは使わせてもらいましょう。
稀に過年度の定期考査を対策プリントとして使っている塾がありますので注意が必要です!
②解答(丸付け)のことを考えて作る
考査の作成は、解答(丸付け)まで考えて作ることを強くお勧めします。
わかりにくい記号の羅列は自分の首を絞めるだけです。思い切って「アアアア」「アイウエ」など、考えなくても丸付けできる羅列にしましょう。
また、記述問題は可能な限り解答が複数あるものはやめましょう。担当教科(科目)の先生が複数人いる場合、模範解答と別の解答がある場合相談をしなければいけません。
それだけで仕事が滞ってしまうので複数解答ありの記述問題は控えましょう!
③事前に作成する
学期が始まる前に試験を作成することを強くお勧めします。
事前に試験作成をすることで教えることが整理されて効率よく授業を進めることができます。定期考査では、応用(初見)問題を20〜30%(学校による)出題すると思いますが、事前に作成しておけば、そのバランスを考えて授業を進めることができます。
一方で、「事前に作成すれば試験のことだけを教えてしまうのではないか」と懐疑的な先生も散見されますので、これは完全に好みですね!!

期日が迫っていないとやる気が出ない先生!その気持ちはわかりますが、平日に遅くまで残るよりも学期が始まる前の少し時間のあるうちにコツコツ進めておきましょう!
オススメ書籍
最後に
今日は「【中学校・高校】定期テスト(考査)の留意点と効率的な作り方」をお伝えしました。
改めて文字化することでテスト作成時に気をつけることが再認識できましたよね。お忙しい皆さんの参考になればと思います。
本日は以上です。お読みいただきありがとうございました。もしよろしければ下のランキングをポチッと押していただけるとありがたいです。





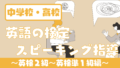

コメント