みなさんこんにちは、草食系高校教師です。
今日は「【中学校・高校】英語授業中の発音指導の実践例(英語の早口言葉) 〜多様性と重要性〜」をお伝えします。
英語科のみなさん、授業中に発音指導することはありますでしょうか。
おそらく、「新出単語導入の時や音読の時にちょっとだけ指導する」という方が多いと思います。
また、「多様性の時代だから日本語発音でもいいのではないか?」という発音指導に懐疑的な方は指導自体していないのかもしれません。
教員も10人10色なのでどんな考え方を持っていてもいいと思います。
さて今日は私が実際に行っている発音指導の実践例を軸に、多様性と英語・発音指導の重要性をお伝えします。

是非見てねー!!!
多様性と英語

まずは「多様性と英語」を見ていきましょう。
みなさん、ここ5年くらいで「多様性・多様性時代」という言葉をよく聞くようになりましたよね。
これは、障がいのある人や高齢者の雇用、女性の活躍促進、LGBTQなどの性的マイノリティなど、どんな属性・特性の人も、誰もが自分らしく生きられる社会のことを指します。
平たく言えば、「みんな違ってみんないい」ということだと思います。
この多様性の流れは英語の世界にも波及しています。
以前までは、英語の教科書で使われる英語は「アメリカ英語」、TOEICやその他検定試験では「アメリカ英語」と「イギリス英語」が主流でしたが、現在は「カナダ英語」「オーストラリア英語」「ニュージーランド英語」などの英語が登場するようになりました。
5年ほど前にGTEC for studentsで「日本英語」が使われていたのはとても驚きました。
最近では英語の多様性からか、Englishを複数形にした「World Englishes」という言葉が登場しました。
国名とEnglishを文字り、「Singlish(Singapore+English)」「Konglish(Korea+English)」という言葉が作られ、同様に日本語も「Japanglish(Japan+English)」や「Janglish(Japan+English)」と言われるようになりました。
さらに、日本語(日本語だけではないかもしれない)は「L」と「R」が混同しやすいことから「Engrish」と半ば揶揄されているような言葉さえ登場しました。
これらの英語界の動きを見ると、「発音に捉われなくてもいいよー!」というメッセージなのではないかと思います。

しかし、発音を伸ばすことで得られるメリットはあるのではないでしょうか!それでは見ていきましょう!
発音指導の重要性

次に「発音指導の重要性」を見ていきましょう。
上記のように、世界では様々な英語が使われており、日本語発音が悪いとは思いません。それも多様性の1つだと思います。
しかし、多様性の時代とは言っても基本的な英語の発音は世界共通ですし、向上させることで得られるメリットは少なからずあると思います。
それでは2つのセクションに分けてお伝えします。
①読めない単語(発音)は聞き取れない(聞き取りにくい)
私がよく生徒に言っているのは「読めない単語は聞き取れない」です。
例えば「無花果」という漢字。
「むかか」と読んでいては「いちじく」と言われた時に理解できませんよね。
そういうことなんです。(ドヤ!)
英語に置き換えると、
例えば「make」。
「マケ」と読んでいては「メイク」と言われた時にわかりませんよね。
そういうことです。(ドヤ!Part2)
②綴り(スペリング)を想像できる一助になる
発音ができるとスペリングを容易に想像できるようになります。
例えば、「Delivery」という英単語。
カタカナで読めば「デリバリー」なので、生徒は「Delibery」「Deribely」「Deribery」など、「LとR」「bとv」を間違って書く傾向があります。
その場合、発音の方法を理解しておけば、口の中の動きでスペリングを想像できるようになります。
私自身も「squirrel」「literally」など、特にrとlが複数使われている単語はスペリングに悩むことがあります。その場合、口の動きから想像して書くようにしています。
私は授業中に以下のような説明をして日本語にはない発音の方法を伝えています。
L=舌先を上前歯の裏にくっつけてラリルレロ
R=口をすぼめて、舌が口内のどこにもつかない状態でラリルレロ
F,V=下唇を噛んでF,V(Vはブイではない)
TH=上下の前歯で舌先を挟みサシスセソ
*本来はもっと日本語にはない音がありますが、これは一例です。
本来はもっと詳しい説明が必要かもしれませんが、発音だけの授業ではないので簡単な説明をして繰り返し練習するようにしています。
授業中の練習内容と方法・確認

次に「授業中の練習内容と方法」を見ていきましょう。
練習内容
本来、1個ずつ丁寧に練習していけばいいのでしょうが、そんな時間はカリキュラム上ほとんどありません。
そのため私は手っ取り早く、早口言葉を使って練習することがあります。
英語の早口言葉は「Tongue Twister」で検索すればたくさん出てきます。
ここでは私が使っているものを一部紹介します。
〜LとRとF〜
→Freshly fried fresh flesh(油であげたての新鮮な肉)
〜VとB〜
→Vivian believes violent, violet bugs have very big value.(ビビアンは乱暴なすみれ色の昆虫には大きな価値があると信じている)
〜SHとS〜
→She sells seashells by the seashore.(彼女は海岸で貝を売る)
〜THとFとR〜
→He threw three free throws,(彼はフリースローを3回投げた)
これらの例文はよく使います。
生徒は面白がってたくさん練習しますし何よりも盛り上がります。
練習・確認方法
私の練習方法は以下の通りです。
- 全体練習
- 個人練習
- 個別確認
*一人ずつチェック
全体練習では、重要なところを以下の方法で細かくしつこく行います。
教員は下図のように列ごとに教室を周り、1人1文ずつ発音するのを確認していきます。(生徒は2列ずつ起立する)
発音し終わったら教員がその場で1〜5(5が最高)までの数字か、OKかNot OKかを生徒に伝えます。
前者は、事前に配布しておいたワークシートに生徒が自ら記入します。後者は、OKの生徒だけ着席し、Not OKの生徒は2列全員が終わるまで起立して置きます。全員が終わった時点で教員が誰がNot OKなのかメモを取って置きます。
そのメモを元に、次の授業で再度確認するようにしています。

教員が2列ずつ確認する間、他の生徒は個人練習をするように促していました。教室が静まっている状態だと発音する生徒が緊張してしまうからです。
この活動は、授業の集中力が途切れる真ん中くらいから取り入るようにしています。特に、午前中に体育があった5時間目6時間目の授業の時は積極的に取り組んでいます。なんでかって???
そういう時の授業は無理だから!無理!無理!!ムーーリーーー。教員ならわかるはず!!
導入から生徒一人ずつ確認(40人クラス)まで15分くらいで終わりますし、何よりも1人ずつ確認するので強制的に活動させるという狙いもあります。
オススメ書籍

それではオススメ書籍を紹介します。
最後に

今日は「【中学校・高校】英語授業中の発音指導の実践例(英語の早口言葉) 〜多様性と重要性〜」をお伝えしました。
私はELLEGARDENという日本のロックバンドの綺麗な英語の発音に憧れて英語を勉強し始めました。
「うおーー、発音かっけええ!」から、今は中高英語科教員でTOEICは945点取ることができました。
発音から英語を勉強し始める人は稀有かもしれませんが、何が夢中になるトリガーになるかはわかりません。何が生徒の知的好奇心にキャンプファイヤー並みの火を灯せるかは誰にもわからないのです。
ダルビッシュ並みの変化球の種類を操り、いろんな角度からアプローチしてみましょうよ!私も頑張ります。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。他に記事は450個あるので是非ご覧ください。
もしよろしければこのサイトの支援をお願いします!!金くれ金!!笑





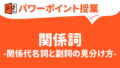
コメント