みなさんこんにちは、草食系高校教師です。
今日は「【中学校・高校】学力差に対応した授業展開(学力指導) 〜一斉授業での取り組み〜」をお伝えします。
クラスには「勉強が得意な生徒と得意ではない生徒」が必ずいます。
私が勤めていた私立の超進学校でさえ学力格差は激しく、学力の二極化が顕著だったのを記憶しています。
2対6対2の法則(働きアリの法則)はどの集団にも当てはまり、我々教員は学力格差を埋めるため、そして学力の底上げを図るために頭を悩ませています。
今日は私がこれまで取り組んできた授業内・授業外にできる学力差を埋めるための方法をお伝えします。

少しでも参考になれば嬉しいです!
学校側の取り組み
まず初めに、一教員ができる取り組みではなく、学力差を埋めるために学校側が行っている解決策を2つお伝えします。
①習熟度別授業
1つ目は習熟度別授業です。
習熟度別授業は「生徒をレベル別にクラス分けをして行う授業のこと」です。
定期考査・実力テスト・模試の成績などをもとに、生徒を習熟度別に、数グループ(生徒数と教員数による)に分けて授業を行います。基礎・標準・発展などと言った名前で集団を分けて行っています。
これの狙いとしては、勉強が得意な生徒は「得意を加速するため」、そして勉強が得意ではない生徒には「底上げを図るため(不得意を普通にするため)」だと考えられます。
習熟度別ではない一斉授業では、簡単な問題も難しい問題も扱います。したがって、勉強ができる生徒もできない生徒も必ず「退屈な時間」が生まれてしまいますのでそれを解消するためという見方もあるかもしれません。

習熟度別授業のメリットを見ていきましょう。
この方法のメリットは生徒の「できた!」が増えることではないかと考えています。特に、勉強が得意ではない生徒の授業では、背伸びした授業展開をしないため、習熟度別ではない授業よりも難しい問題を扱いません。
その結果、生徒の「できた!」が増えます。つまり、生徒の成功体験が増えるということです。この成功体験は学びをブースとしてくれる最高のトリガーだと思っています。
成功体験の積み重ねが学びの楽しさにつながり、それが継続した学習習慣につながると思います。もちろん、時間やお金をかけてすぐに結果が出ないもどかしい期間(現実と理想のギャップの期間)があるかもしれません。
しかし、1度感じた成功体験は、最終的にシンギュラーポイントに到達するのではないかと思っています。
②講習
2つ目は講習です。
講習は、以下のような時間や場面で行われます。
- 放課後
- 夏期
- 冬期
- 春期
- 検定前
そして、これらの多くは上記のように習熟度別や単元別に行われます。
例えば、
- 難関大学英語
- 日東駒専(産近甲龍)英語
- 基礎英語
- 準動詞
- 英検2級
のような講習が行われています。
狙いは、生徒に”合格”の2文字を勝ち取って欲しいためと学校側が「生徒のためにこんな講習開いてますよ」と保護者へのアピールと生徒募集のためです。
後者に関しては話がずれてしまうので以下をご覧ください。
学校の取り組みとしては、学力の二極化を防ぐために習熟度別の授業と講習を行っていることがあります。
一教員の取り組み
それでは、私が取り組んでいる授業内・授業外で学力格差を埋めるために行っていることを3つ紹介します。
これは、上記で紹介した習熟度別に分けたクラスで行うものではなく、通常クラス(分けていないクラス)で行うものになっています。
①レベル別学習(授業内)
1つ目は「授業内レベル別学習」です。
簡単に言うと「授業で扱う問題を3段階(基礎・標準・発展)に分ける学習」です。少し手間ですが、私は基本的にレベル別に分けた3枚のプリントを用意します。
これの狙いは2つあります。
①退屈な時間を作らないこと
②生徒の「できた!」を増やすこと
「できる子をさらに伸ばし、できない子を少しできるようにする」というのが全教員が思っている授業の本懐だと思います。
それを少しでも授業内に達成するためには授業内レベル別学習、かっこいい言い方をすれば個別最適化学習ではないでしょうか。
この授業展開をする時は、「終了した生徒から前に提出する方法」をとることがあります。問題を早く正確に解く生徒がいる一方で、熟考して答えを導く生徒がいます。つまり、問題を解くスピードには大きな差があります。
生徒には終わったから待つのではなく、どんどんどんどん先に進んで多くの問題に触れて欲しいと思っているのでこのスタイルをとることがあります。
この方法のいいところは、生徒一人一人を見ることができるので、生徒がどこで躓いているのかを見て感じることができるところです。教員は、生徒がどのようにこの問題の答えを導き出したのかを詳しく知ることができ、その場で気づきを与える声かけをすることができます。
この授業スタイルは残念ながら少人数向きです。
②教え合い学習(授業内)
2つ目は「教え合い学習」です。
これは名前の通り「生徒同士が教え合う」ことです。
先生の中には「教え合いは教える生徒の時間を搾取している」と考える人も散見されますが、問題を解くことだけが学習ではないと思いますし、私は他人に何かを教えることは教える側にも気づきをもたらすと考えています。
以下の平均学習定着率を表す学習ピラミッドにあるように「Teaching Others=他人に教えること」は定着率が90%です。

他人に教えるということは根本を理解していないとできないことです。教える側は能動的な学習をすることができます。
教わる側も友達やクラスメイトから教わるので、教員が教えるよりも親近感が湧きますし素朴な疑問をぶつけることができるでしょう。
③動画学習(授業外)
3つ目は「動画学習」です。
これは、生徒が授業外(学校や自宅)で動画を見る学習です。
私が勤めていた学校では、教員と生徒の共有フォルダに単元ごとの授業動画を教科ごとにアップしていました。当初はコロナ禍での学び確保のためでしたが、反転授業にも使えるということでアップしたままという運びになりました。
動画は一本10分程度で、単元を細かく分けて動画を撮影していました。
例えば、
〜動名詞〜
①動名詞3つの働き
②進行形と動名詞
③前置詞の目的語
④動名詞の動作主
⑤所有格と目的格
⑥目的語に来る動名詞と不定詞
⑦動名詞の不定詞の特徴
このような形で動画を作成していました。

動画作成するのは難しいですよ。。
わからない生徒には具体的に「仮定法過去完了の倒置の動画を確認して!」と指示を出すこともありました。
④問題学習(授業外)
最後は「問題学習」です。
これはGoogleフォーム・ロイロノート・Classiなどにアップされた問題を解答する学習です。
これも上記の「③動画学習」同様に、教員が単元ごとに作成した問題を生徒がいつでもどこでも問題を解くことができるシステムです。解答も次ページに載せているのですぐに確認することができます。
その後、教員に質問がある場合はアプリ(私はロイロノートやZOOMを使っていました)を介して連絡することができます。
オススメ書籍
最後に
今日は「【中学校・高校】学力差に対応した授業展開(学力指導) 〜一斉授業での取り組み〜」をお伝えしました。
学力差を埋めるための取り組みは授業内のみならず、授業外でも行うことができるようになりました。机上での勉強が苦手な生徒は、タブレットやパソコンなどの電子端末を使うことでやる気になる生徒もいます。
せっかくICT改革で得た素晴らしい武器ですので使わない天はありません!ぜひ参考にしていただけると幸いです。
本日は以上です。お読みいただきありがとうございました。もしよろしければ下のランキングをポチッと押していただけるとありがたいです。






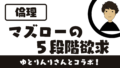

コメント