こんにちは、草食系高校教師です。
今日は「【中学校・高校】英語読解授業(英語コミュニケーション)の方程式 〜英語を読む力とは?〜」をお伝えします。
みなさん、英語読解授業はどのように進めているでしょうか。
授業に正解はないのでどのような進め方でも間違っていないと思います。
しかし、授業に対して教科内で話し合うことが経験上ほとんどないので自分の授業に悩むことがみなさんあると思います。
私も同じです。
自分の授業に100%自信がある人はヤバいやつです。笑 (生徒の前では自信があるようには振る舞うのは言わずもがな。)
さて、今日は「英語読解授業はこんな感じなんじゃないのー?」ということをお伝えしたいと思います。
私の考えが正解だとは思いません。
一つの引き出しだと思ってください。

考え方は人それぞれ。
ターゲット生徒
まずは「ターゲット生徒」を見ていきましょう。
「以下の話はこんな生徒を想定して話をしていまっせー」と、画面越しの皆さんが受け持つ生徒にフィットする話かどうかを判断してもらえたらと思います。
私が担当する1つのクラスを想定しています。
学校:男女共学
生徒レベル:偏差値38〜55(英検で言えば4級〜2級)
生徒観:クラスの半分以上はやる気がなく英語の授業に対してネガティブ
生徒それぞれのモチベーションやレベルの高低差が激しくて耳がキーンとします。
一般的な公立中学校のような生徒層になります。
偏差値30〜70程度(京大合格)まで教員生活の中で担当してきました。
1番難しい層は、偏差値40〜50程度だと思います。そして1番多い層でもあります。
そんな生徒を伸ばすための考え方を以下でお伝えします。
英語コミュニケーション授業の狙い
まずは「英語コミュニケーション授業の狙い」を見ていきましょう。
令和4年度より学年進行で実施されている学習指導要領には以下のことが書かれています。
◯英語で「聞く・読む・話す(やり取り・発表)・書く」の4技能5領域を統合的に育成すること
◯「言語活動」を通して、英語でコミュニケーションを図る力を育てること
◯多様な文化や価値観への理解を深めること
◯英語での「思考・判断・表現」の力を育てること
は?無理じゃね?
最初に見た時はそう思いましたよね。
そうなんです。無理なんです。
4技能5領域を満遍なく扱いたい気持ちはありますが、ある一定の生徒層以下には難しいと思います。できたとしても全てが中途半端になってしまいます。
私は私立に勤めていることもあり、学校存続のために進路実績を上げなければなりません。そのためには4技能5領域満遍なくではなく、受験に出てくる英語を扱うしかありません。
それではこの記事の本題である「英語読解授業の方程式」を見ていきましょう。
英語読解授業の方程式
まずは「英語読解授業の考え方」を見ていきましょう。
上記のように受験英語を多く扱うことを想定して話をしていきます。
大学入試の鬼門であるセンター試験が大学共通テストに名前が変更され、同時に出題形式が大きく変わりました。
その結果、発音アクセント問題・文法穴埋め問題・整序語句問題がなくなり、読解問題だけが出題されるようになりました。
その傾向は各大学の一般試験や推薦入試にも影響を及ぼしています。(一部違う)
そうなると、学習指導要領にある「4技能5領域の育成」ではなく、学校存続の鍵となる進路実績を上げるために自ずと「リーディング中心」にシフトチェンジせざるを得ません。
さて、前置きが車で静岡を横断するくらい長くなりましたがリーディング中心の授業の考え方をお伝えします。
個人的に以下の方程式が成り立つと思います。
「英語を読む力=語彙力+文構造の理解+背景知識+読解戦略」です。
ジェフ・ウィリアムス(J)、藤川球児(F)、久保田智之(K)のJFK並みの勝利の方程式です。
「リーディング力=ただ読むこと」ではなく、「戦略的に、背景と語彙を意識しながら読む力」を育てることだと思います。
現実的に、この4つは授業で扱えると思います。
それぞれが具体的にどういった内容かを以下で見ていきましょう。
語彙力の強化:授業で扱う語彙だけでなく、単語帳(ターゲット、ユメタンなど)を導入する。
また、接頭辞・接尾辞、語源を扱うことで推測力も高める。
文構造の理解:読みにくい文章(関係詞、分詞構文、倒置など)の読む方法や文型を導入する。
背景知識の補完:英文の文化的背景やトピックに関する知識を導入する。調べたり考えたりする。
読解戦略の習得:スキミング(大意をつかむ)、スキャニング(特定情報を探す)、
スラッシュリーディング、要約などの技術を意識的に教える。
私はこの4つを軸に授業をしています。
生徒が「読める」→「分かる」→「楽しめる」に変わっていくよう、段階を意識した指導が大切だと思っています。
しかし、この「読める」→「分かる」→「楽しめる」を作るのがフェルマーの定理くらい難しいのです。
読解授業ではこの4つを軸にそれぞれの精度を高めて行くのが必要なのかもしれません。

授業に正解はない。だから大変だけど楽しいのですなー。
オススメ書籍
最後に
今日は「【中学校・高校】英語読解授業(英語コミュニケーション)の方程式 〜英語を読む力とは?〜」をお伝えしました。
ハイレベルな学校のハイレベルな実践例はインターネット上にたくさん落ちています。しかし、それを勤務校で実践できる教員は一部だと思います。
私は生徒層が1番多い偏差値40〜50程度の生徒の実践例がもっと増えたらいいなと思っています。ぜひシェアしましょう。
本日は以上です。お読みいただきありがとうございました。もしよろしければ下のランキングをポチッと押していただけるとありがたいです。









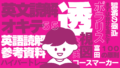
コメント